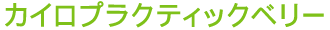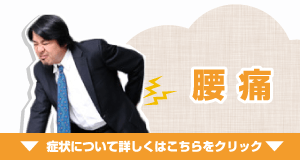脚のしびれの原因と考えられること

足のしびれ(しびれ・シビレ)は、とても不快で日常生活にも影響しやすい症状です。周りから理解されにくいこともあり、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
このページでは、医療機関の受診が必要なサインと、足のしびれに関係する主な原因、そして当院で行っている評価・サポートについてわかりやすくご紹介します。※当院の施術は医療行為ではありません。
まずは医療機関での確認を
足のしびれの中には、早めの受診が望ましいケースがあります。次のような症状がある場合は、できるだけ早く医療機関を受診してください。
- 体の片側の手足に同時にしびれ・脱力が出る、言葉が出にくい・ろれつが回らない、物が二重に見える
- 急に排尿・排便がしづらい、会陰部の感覚が鈍い(馬尾症状が疑われる場合)
- 顔面のしびれや歪み、激しい頭痛やめまいを伴う
- 発熱や強い痛み、外傷後のしびれが続く
受診先の目安:整形外科/脳神経外科/内科・神経内科/泌尿器科など、症状に応じてご相談ください。
足のしびれの主な原因(例)
しびれはひとつの原因だけで起こるとは限らず、姿勢・神経・血流・生活習慣など複数の要因が重なって出現することがあります。以下は代表的な例です。
① 神経の影響が考えられるもの
- 腰椎の変化や椎間板の変性に関連する坐骨神経の刺激(いわゆる坐骨神経痛)
- 脊柱管狭窄が疑われる状態(歩くとしびれ/休むと楽など)
- 梨状筋まわりの過緊張による神経の圧迫傾向
- 腓骨神経の絞扼(膝外側〜足の甲のしびれなど)
- 足根管症候群(内くるぶし付近での神経絞扼に伴う足裏のしびれ)
- 末梢神経の代謝性障害(糖代謝の乱れ、飲酒、ビタミンB群不足 など)
- 薬剤性のしびれ(処方薬や抗がん剤などの副作用によることがある)
② 血流・血管の影響が考えられるもの
- 下肢の血流低下(閉塞性動脈硬化症などが疑われる場合)
- むくみ・冷え・長時間の同一姿勢による循環の滞り
③ 筋・筋膜・関節バランスの影響が考えられるもの
- 長時間の座位・立位・片寄った姿勢の習慣(骨盤・背骨のアライメント変化)
- 股関節や足関節の可動性低下、ふくらはぎ・お尻まわりの過緊張
- 靴のサイズや形状(先の細い靴、硬いソールなど)による圧迫
- 筋膜由来のトリガーポイントに関連する放散感
④ そのほかの要因
- ビタミンB12不足、甲状腺機能の低下などの内科的要因
- 睡眠不足、ストレス反応や自律神経の乱れ
- 脱水や電解質バランスの乱れ(発汗・利尿薬・食事内容など)
「ヘルニア=必ずしびれる」というわけではなく、画像所見と症状が一致しないこともあります。大切なのは、現在の症状と生活背景を踏まえた丁寧な評価です。
腓骨神経の絞扼や足根管症候群について
しびれの原因には、腓骨神経の絞扼(膝外側〜足の甲にかけてのしびれ)や、足根管症候群(内くるぶし付近での圧迫による足裏のしびれ)といった末梢神経のトラブルもあります。
これらはまず医療機関での診断が大切ですが、そのうえで筋肉や関節のアンバランス、姿勢や歩き方のクセなどが関わっている場合、カイロプラクティックでの調整やセルフケアの工夫がしびれの軽減や再発予防に役立つこともあります。
一人ひとり原因や状態が異なりますので、評価に基づいて最適な方法を一緒に考えていくことが大切です。
部位で変わる“原因のヒント”
- お尻〜太ももの後ろ〜ふくらはぎ〜足裏:坐骨神経経路に沿うケースが多い
- 足の甲・外くるぶし周辺:腓骨神経の影響が疑われることがある
- 足裏のしびれ・灼熱感:足根管付近の影響が疑われることがある
上記はあくまで目安です。実際は複合要因であることが少なくありません。
当院で行う評価とサポート
カイロプラクティックベリーでは、状態を見極めるために次のような評価を組み合わせます。
- 姿勢・動作の観察、関節可動の確認(モーション/スタティックパルペーション)
- 整形外科的検査、神経学的検査、筋力・知覚のチェック
その上で、負担の少ない範囲での関節モビリゼーション・筋膜ケア・神経の滑走(スライド)を促すエクササイズ、日常動作の工夫などをお伝えします。
医療機関での治療を優先すべき所見がある場合は受診をご案内します。
ご自宅でできるセルフケアの一例
- 同じ姿勢が30〜60分続いたら、いったん立つ/軽く歩くなど姿勢を切り替える
- 脚を強く組む・きつい靴を長時間履くことを控える
- お尻・ふくらはぎのやさしいストレッチ(痛みが強い時は中止)
- 水分と栄養(特にタンパク質・ビタミンB群)を意識する
セルフケアは状態に合った方法を選ぶことが大切です。無理はせず、評価のうえで調整していきましょう。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. しびれは必ず良くなりますか?
A. しびれの背景はさまざまで、経過にも個人差があります。評価に基づいて「何が影響しているのか」を整理し、できることから整えていくことで、軽減が期待できる場合があります。
Q2. どのくらい通えばよいですか?
A. 状態や生活習慣によって異なります。セルフケア等と組み合わせて調整していきます。
Q3. 医療機関で「異常なし」と言われましたが、しびれはあります。
A. 画像や血液検査では異常が見つからないケースでも、筋肉・関節・神経の動きや姿勢のバランスが関連している場合があります。評価に基づいて生活習慣や体の使い方を見直すことが役立つこともあります。
磐田市・浜松市・袋井市近郊で、足のしびれや腰の不調のご相談は、カイロプラクティックベリーへお気軽にどうぞ。
医療機関での検査結果をお持ちの場合は拝見し、内容を踏まえて丁寧にお話を伺います。
ご予約・無料相談はこちら